一隅の経営について
|
128-01
|
このRISHO NEWSに掲載されている「一隅の経営」は、私が自身で執筆しているものではありません。私が社内の会議などで話したことを社員がメモをとっていて、それをまとめたものです。
私が利昌工業に入社したのは1951(昭和26)年のことで、21歳でした。その頃の利昌工業で学卒らしい学卒は私と兄だけです。老練な番頭さんといった社員もいません。多くの企業では敗戦を機に故郷に帰るなどして従業員が退職していました。
利昌工業は戦争中、海軍の軍需工場でした。その海軍がなくなったので、得意先を全て失ったのと同じような状態でした。このような中、利昌工業を伸ばしていくには、これから学卒も必要だと考え、私が入社した翌年から学卒を採用していきました。
しかし、私も含め20代の若造ばかりです。私は焦りました。まず私が勉強して大人のものの考え方を身につけねばなりません。ずいぶん本を読みました。あらゆる分野の本を一日一冊のペースで読んでいた時期もあります。そして自分の身につけたものを、今度は一刻も早く部下に教えねばなりません。何故なら一人でやっているだけではパワーになりません。私も含めて皆のレベルを早急に引き上げる必要があったのです。学ぶと同時に教えるという、生徒と先生の二役をやっていたわけです。そのため、問題が起こると徹底的に考えるという訓練もでき、その後もいろいろな話を社内でする習慣ができたのだと思います。
私は原稿なしに喋るだけで、記録するように指示したことは一度もありません。聞いている社員はメモをとっていたようで、残っているものは代表取締役に就任した直後の1971年から今日までの約50年分です。
もとよりこれは社内用であり、利昌工業の従業員のためにと思って喋っていることですから、社外の方にお見せするものではないのです。
活字になったのは「利昌工業社報」(写真)に、「利倉社長の語録」として掲載されたのが最初です(1987年)。会議で直接、私の話を聞いた人だけでなく、全社員に知らせる意味で連載されました。
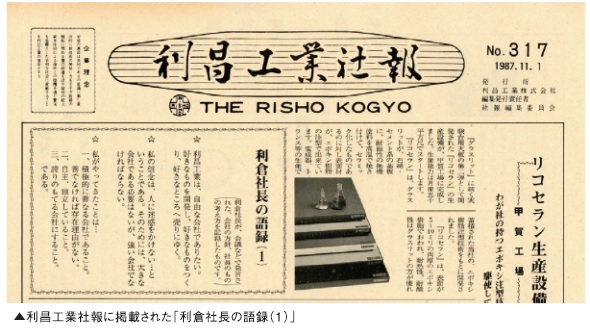
今ご覧いただいている「リショーニュース(RISHO NEWS)」は7500部を年4回発行。得意先、仕入れ先、関係官庁、学校などにお送りしております。当初は新商品を紹介する「プロダクツ・ニュース」、新しい技術を紹介する「テクニカル・レポート」、当社の商品が社会のどのようなところでお役に立っているかを紹介する「社会と利昌」などで構成されていました。
ところが編者が私の語録のうち、社外の人に見て頂いてもオモシロイのではないかというものを選び「一隅の経営」というタイトルをつけて掲載を始めたのです。1993年の94号からです。
そうしますとテクニカル・レポートなどは難しくてわからないが「一隅の経営」は長年、経営の第一線で取り組んでいる人が、ものごとの本質を自分の体験から出た言葉で語っているから結構参考になる…との反響を得て、約30年続いているような次第です。
古い語録を一部紹介させて頂きます‥
|
放漫経営
|
128-02
|
|
問題が発生した場合は、その場で解決しなさい。その場で解決するクセがついていないと後々までExcuse(言い訳)ばかりしていなければならない。その場での解決というのは、その時点では多少損かも知れないが、結局徳な場合が多い。世に放漫経営というのはその場で解決しなければならない問題を、後ヘズラしていったからだ。(1971年)
|
NOと言えて一人前
|
128-03
|
|
人気とりじゃないんだから…きびしい事も、イヤな事も言わねばならない。NOと言えないようでは一人前じゃない。お人好しはプライベイトのみにしてもらいたい。(1975年)
|
商売
|
128-04
|
|
品質がよくて、安くて、熱心なら、敵(かたき)でも買ってくれます。悪くて、高くて、不熱心なら、親でも買いません。(1975年)
|
部下の指導
|
128-05
|
|
よい先生というのは、能力のある先生ではない。熱意のある先生である。部下の指導で大切なのは熱意である。(1977年)
|
結論は先に出ている
|
128-06
|
|
やっているうちに、こうなりましたというのは管理ではない。管理とは結果が先に出ていて、そこへもっていくのが管理である。仕事というのは結論が先に出ていなければならない。(1977年)
|
それでも起こったらどうなる?
|
128-07
|
|
経営者は常に危険を予知する能力をもたなければならない。臆病なくらいにやっていてちょうどよい。臆病と卑怯とは違う。起こるか起こらないか…この議論は技術者がやっておればよい。経営者は、それでも起こったらどうなるか…常に冷静に考えていなければならない。(1978年)
|
売り手と買い手
|
128-08
|
|
初めから買ってくれると思ってゆくから根本的な間違いを起こす。販売とは、売ろうという意志と、買わないという意志との戦いである。(1979年)
|
異常と正常
|
128-09
|
|
何が異常で、何か異常でないか判断できないようではダメだ。正常がわからないから異常もわからなくなる。(1979年)
|
数学ができる子と、絵の上手な子
|
128-10
|
|
数学ができる子供と、数学は駄目だが絵の上手な子供…どちらが上とか下とかいうのはおかしい。(1984年)
|
知ること
|
128-11
|
|
知ることは不安であるが、早く知れば、助かるかもしれません。(1989年)
|
悪い話、良い話
|
128-12
|
|
悪い話ばかりの時は「しかし、どこか良いところがないか」と考えてみましょう。良い話の時は「しかし、どこか悪いところがないか」と考えましょう。(1997年)
|
自分にあう仕事はない
|
128-13
|
|
最近の学生は、会社に入ってもすぐ辞めてしまう人が多い。辞める理由は、仕事が自分の好みにあわないからといいます。しかし、自分の好みにあう仕事などありません。自分がその職業にあわせてゆくのです。誰がその人にあう職業などつくってくれるものですか。
自分から好きにならねばなりません。あわせてゆくことが忍耐なのでしょう。そして徐々に理解もできて好きになっていけると思います。
仕事をイヤイヤするのも一生。仕事が好きになって頑張るのも一生。(2016年)
|

